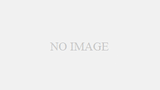ITパスポート 令和6年度 公開問題 問40 について解説します。
問題
問40 アジャイル開発に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 開発する機能を小さい単位に分割して、優先度の高いものから短期間で開発とリリースを繰り返す。
イ 共通フレームを適用して要件定義、設計などの工程名及び作成する文書を定義する。
ウ システム開発を上流工程から下流工程まで順番に進めて、全ての開発工程が終了してからリリースする。
エ プロトタイプを作成して利用者に確認を求め、利用者の評価とフィードバックを行いながら開発を進めていく。
解説・解答
アジャイル開発とは、変化に柔軟に対応しながらソフトウェアを少しずつ素早く作っていく開発手法です。
・小さな機能単位で開発・リリースを短期間(1〜4週間)で繰り返す
・利用者のフィードバックをすぐ反映して、どんどん改良していく
・ゴールも「柔軟」に見直しながら進められる
アジャイルの特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 反復的開発(イテレーション) | 短いサイクルで開発とテストを繰り返す |
| 優先度重視 | ユーザーにとって価値の高い機能から作る |
| 顧客との協調 | 顧客の声を頻繁に取り入れる |
| 柔軟な変更対応 | 要件変更に柔軟に対応できる |
| 自律的チーム | チーム全員で設計・実装・テストに関わる |
それぞれの選択肢について確認します。
ア: 開発する機能を小さい単位に分割して、優先度の高いものから短期間で開発とリリースを繰り返す。
アジャイル開発の中核的な考え方に合致しています。これが正解です。
・「小さな単位(イテレーション)」で「優先度の高いものから」進めます。
・開発→評価→リリースのサイクル(スプリント)を短期間で何度も繰り返すのが特徴です。
・スクラムやXP(エクストリームプログラミング)などのアプローチでよく見られます。
イ: 共通フレームを適用して要件定義、設計などの工程名及び作成する文書を定義する。
これは「共通フレーム(共通フレーム2013など)」という日本の標準化文書の説明で、ウォーターフォール型開発の説明に近いです。
文書中心・工程順序が重視されるモデルで、アジャイルの柔軟性とは対照的です。正解ではありません。
ウ: システム開発を上流工程から下流工程まで順番に進めて、全ての開発工程が終了してからリリースする。
これは典型的なウォーターフォールモデルの説明です。アジャイル開発では、全工程を一気にやってからリリースするのではなく、小さく分けて都度リリースしていきます。正解ではありません。
エ: プロトタイプを作成して利用者に確認を求め、利用者の評価とフィードバックを行いながら開発を進めていく。
これはプロトタイピング開発モデルに近い説明です。一見正しそうですが、正解ではありません。
以上により、この問題の解答は「ア」になります。