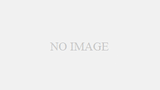ITパスポート 令和6年度 公開問題(過去問) 問84 について解説します。
問題
問84 IoTエリアネットワークでも利用され、IoTデバイスからの無線通信をほかのIoTデバイスが中継することを繰り返し、リレー方式で通信をすることによって、広範囲の通信を実現する技術はどれか。
ア GPS
イ MIMO
ウ キャリアアグリゲーション
エ マルチホップ
選択肢 ア : GPS
GPS(Global Positioning System)は、位置情報を取得するためのシステムです。デバイスの「どこにあるか」を知るためのもので、通信の中継やデータ転送とは関係ありません。
選択肢 イ : MIMO
MIMO(Multiple Input Multiple Output)は、複数のアンテナを使って、通信の速度や安定性を向上させる技術で、Wi-FiやLTE、5Gなどで使われています。あくまで「基地局と端末の単一リンクの品質向上」が目的で、複数ノードを経由しません。中継やリレー通信とは無関係です。
選択肢 ウ : キャリアアグリゲーション
キャリアアグリゲーション(CA)は、LTE-Advanced以降で採用されている技術で、複数の周波数帯域(キャリア)を束ねることで、通信速度を上げます。IoTやセンサーネットワークのような低電力・低帯域環境では使われにくい技術です。「単一ノードと基地局間の高速化」の話であり、中継やリレー通信とは無関係です。
選択肢 エ : マルチホップ
これが正解です。マルチホップ(Multi-Hop)は、通信データが複数の中継ノード(IoTデバイスなど)を経由して目的地まで届く通信方式です。ノード(IoTデバイスなど)が中継機能を持ち、次々とデータを他のノードにバケツリレーのように渡していきます。1回の通信(ホップ)で届かない遠距離の相手とも、複数回ホップすることで通信可能になります。通常の通信が「1ホップ(単一リンク)」であるのに対し、マルチホップは「複数リンクを連結して使う」方式です。
<特徴>
・センサネットワークやメッシュネットワークなど、広範囲で電力効率の良い通信を実現したい場面で使われます。
・ZigBee や Thread、LoRa Mesh などのプロトコル(IoTにおける代表的な技術)で使用されます。
・各ノードが相互に接続されていて、ルートの一部としても機能します。
・災害時の緊急通信、スマート農業、スマートシティのインフラ監視など、通信インフラが整っていない場所でも使えます。
・通信距離の延長、信頼性の向上、省電力化がメリットです。
解答
以上により、この問題の解答は「エ」になります。